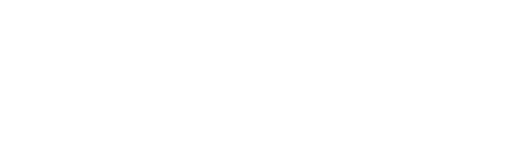心臓内科 朴澤 耕治 インタビュー
謙虚な姿勢を忘れずに診療にあたっています


心臓内科主任部長 兼
心臓血管センター副センター長 兼
末梢血管疾患治療部長 兼
日帰り治療センター長

末梢血管疾患の早期発見と治療
私が専門にしている末梢血管疾患は、動脈、静脈、そして場合によってはリンパ管も含まれる広い範囲の疾患です。末梢血管疾患というと、心臓以外の血管に関連する疾患を指し、これには大動脈も含まれるかどうかは議論の余地がありますが、基本的には心臓の血管と大動脈以外の血管を対象としています。最も一般的なのは、足の動脈における虚血性疾患、つまり動脈硬化によって血管が狭くなる病気です。
足の血管が最も多く影響を受けますが、腎臓の血管や脳梗塞に関連する頸部の血管、鎖骨下動脈なども末梢血管に含まれます。末梢血管の動脈硬化により虚血が起こり、血管が詰まるケースが多いですが、血管が破れることもあります。私たちがよく扱う疾患としては、特に足の動脈、下肢動脈が多いです。
典型的な症状は、跛行(はこう)と呼ばれるもので、歩くとふくらはぎが痛くなることです。これが進行すると、足が冷たく感じたり、痛みやしびれが現れたりするようになります。さらに重症化すると、座っているだけでも症状が出るようになり、血流が悪化します。血流が極端に悪くなると、足に傷ができ、その修復がうまくいかず、感染や潰瘍、最悪の場合は壊疽(えそ)に至ることもあります。壊疽が起きると末期状態で、非常に深刻な状況になります。
ABI検査でわかる血管の健康状態
初期の症状では、足の痛みがどこから来ているのか気付きにくいことが多いです。整形外科的な問題なのか、心臓や血管から来ているのかを判断するのは難しいんです。例えば、同じ跛行症状(歩行時のふくらはぎの痛み)でも、4分の3は整形外科的な原因で、4分の1が虚血によるものです。そして、全体の半分くらいは両方の要因を持っていることがあります。ですから、足に痛みや違和感があれば、どちらの科でも良いので、まず受診することが大事です。

簡単に診断できる方法の一つが「ABI」という検査です。両腕と両足に血圧計をつけ、血流を測るだけのシンプルな検査で、血管の状態を診ることができます。さらに、血管年齢も分かるため、一般の方にも興味を持ってもらえるきっかけになります。検査自体は簡単で、総合病院などでは機械を使って実施可能です。
特に、動脈硬化のリスクがある方は、この検査を一度受けてみるべきです。動脈硬化は、20歳を過ぎると誰にでも起こりますが、その進行スピードは人によって異なります。進行の速さは、糖尿病、高血圧、喫煙、遺伝的要因などが関係しています。これらのリスクがある方は、動脈硬化が進んでいる可能性が高いので、ぜひABI検査を受けて血管の状態を確認することをお勧めします。
カテーテル治療で改善する末梢血管の痛み
治療方法には大きく分けて、バイパス治療とカテーテル治療の2つがあります。どちらが適切かは病状に応じて決まるため、まずはしっかりと診断を受けていただくことが重要です。ただ、多くの場合、カテーテル治療で対応可能です。治療時間はおよそ1時間ほどで、局所麻酔で行います。最近では、鎮静を希望される方も増えており、眠ったような状態で治療を受けることも可能です。

カテーテル治療が成功すると、劇的に症状が改善され、痛みがなくなり、普通に歩けるようになります。通常、次の日から元の生活に戻れ、足の痛みもなくなります。足の痛みは日常生活に大きな影響を与えますが、血管が原因であれば治療によって回復します。
特に、動脈硬化による病気を抱えた方は、リハビリも含めて歩くことが非常に重要です。しかし、足の病気が残っているとリハビリもスムーズに進まず、さらに症状が悪化する可能性があります。足の病気にもしっかりと着目し、悪化を防ぐための治療が必要です。早期に診断し、適切な治療を受けることで、日常生活の質を大きく向上させることができます。
診療にあたり、謙虚な姿勢を大切に考えています
当院の末梢血管治療の強みについて、まず件数が多いことも確かですが、私たちは何よりも「早期治療」と「早期退院」を大切にしています。すべてを迅速に行う方針で取り組んでおり、患者さんをあまりお待たせしないこと、スピード感を持って治療に当たることを重要視しています。これは私たちが特に力を入れている部分です。
ただ、最も大切にしているのは「安全性」です。治療の効果はもちろん重要ですが、今の治療法はかなり成熟しているので、私たちの関心は「いかに安全に治療を終えるか」にあります。安全に治療を進めることが、今でも私たちの目指す最大の課題です。

技術力や豊富な実績があるからこそ、安全性が高まるのは確かです。しかし、そのためには謙虚な姿勢が重要だと思っています。私たちは常に、患者さんと共に治療を進めたいと考えています。患者さんに敬意を払い、一方的に治療を押し付けるのではなく、いつも「どうしたいですか?」と相談しながら進めます。決して「うまくいくから任せてくれ」と押し付けるのではなく、患者さんと「ここまでできるので、一緒にがんばりましょう」と共に歩むことを大事にしています。
治療の進め方についても、患者さんやご家族のリクエストを尊重しながら、最善の方法を提案しています。こちらが良いと思う方法があっても、患者さんが望まなければ別の選択肢を一緒に探すこともあります。こうした相談しながらの治療が、最終的に安全性に繋がると感じています。患者さんとのコミュニケーションを大切にしながら、最適な医療を提供することが、私たちの流儀です。
末梢血管の治療そのものがQOL向上につながる
末梢血管に対して魅力を感じ、この分野を長く続けている理由についてですが、いくつかあります。まず、心臓は「王道」と言われる分野で、多くの医師が取り組んでいます。誰もがやる「王道」を自分がやるのではなく、もっと別の分野に挑戦したいという思いが強くありました。これが一番の理由です。
また、当時の患者さんの中には「心臓の治療はしっかりしてもらえるけど、末梢血管の問題で困っている。どうすればいいかわからない」という声が多くありました。そういったニーズを感じ、心臓以外の分野、特に末梢血管の治療を極めたいと思ったのです。
末梢血管治療に本格的に取り組もうと思ったのは、2008年頃のことです。それ以前から末梢血管の治療は行っていましたが、決定的だったのは、ある患者さんとの出会いでした。末梢血管を担当していた先生が退職され、私が引き継ぐことになった患者さんでした。CTを見た際、私は「これは簡単に治療できる」と誤った判断をしてしまい、ご家族にも「心配しないで治療しましょう」と伝えてしまいました。しかし、後になってそのCTが造影写真ではなく、石灰化して詰まっている血管であることに気付きました。血管が通っているという誤解をしていたのです。
治療に入ってからそのことに気づき、どう対処すべきかと悩みましたが、これまでの少ない経験と知識を駆使して、なんとか無事に手術を終えることができました。その後も引き続きその患者さんを段階的に治療し、他の病院では「足を1本切断しないと治らない」と言われていたところ、最終的には親指1本で済ませることができました。この経験が、自分の感覚が間違っていなかったという自信につながりました。
心臓内科の一部門として、末梢血管治療は非常に重要です。かつては心臓に集中して治療を行う時代でしたが、今では心臓以外の血管治療の必要性が認識されるようになり、さらに患者さんの生活の質(QOL)を向上させることが大事になってきました。例えば、痛みを和らげたり、患者さんに寄り添った治療が求められています。
新デバイスが広げる治療の可能性
末梢血管治療の分野では、長年課題とされていたデバイスラグの問題がありましたが、最近になって日本でも使用できる新しいデバイスが登場しています。いわゆるデバルキングデバイスと呼ばれるプラーク除去デバイスや、血栓を取り除くための道具などがその代表です。血栓や石灰化は血管治療において大きな課題でしたが、これらのデバイスはその問題をある程度解決してくれるものです。特に、昨年や今年にかけて導入され始めた新しいデバイスが、治療の幅を広げてくれています。

変化する医療現場での働き方:共有と調整で組織を活かす
2023年に院長が変わったことにより、病院の体制が変わってからも、私自身や同世代の医療従事者の考え方や姿勢は、それほど大きくは変わっていません。医療への向き合い方や、組織の中での働き方についても、私たちの世代は以前と同じように、真摯に取り組んでいます。しかし、世の中全体が大きく変わりつつあると感じています。特に「働き方改革」の影響は大きく、働きやすさややりがいをどう見出すかという点で、これまでとは全く違う視点が求められるようになりました。
以前は、自分のペースで仕事を進めることができましたが、今は他の人のペースを考慮する必要があると感じています。特に今年度に入ってからは、患者さんのペースを重視することが大きな課題となっています。これまでとは異なり、医師だけでなく看護師や事務職員など、全員のペースに合わせて仕事を進めなければなりません。時には、こちらが他のスタッフに合わせる必要も出てきており、こうしたペースの調整が最終的に組織全体の力を引き出すことにつながるのだと感じています。

合理性という観点でも、以前から物事を合理的に進める必要性は感じていましたが、その範囲が広がったと実感しています。ただ、合理性も人それぞれ異なる基準で判断されることが多く、考え方や「正義」が違う中で、どうペースを合わせるかは難しいと感じます。だからこそ、情報や考え方を共有することが非常に重要です。共有ができなければ、合理的な判断やペースを調整した仕事は難しいでしょう。今は、その共有作業に力を入れている段階です。
現状、まだ道半ばではありますが、全体の約2割はしっかりできていて、8割ほどの進捗があると感じています。ただし、完璧に仕上がるにはまだ時間がかかるでしょう。新しい人が加われば、その影響で雰囲気も変わることがあり、常に変化し続けるプロセスだと思います。変化は難しいですが、それも自然なことだと捉え、これからも共有作業を続けていきたいと思っています。
地域で垣根を越えた情報共有を行いたい
地域全体で協力していくことが大切だと思っています。最終的には、患者さんのためだけでなく、医療に携わるすべての人たちのために、働きやすい環境や目標を持って働けるようにしていきたいと考えています。そのためには、情報や考えをしっかりと共有することが重要です。これまでは、思想や政治的な違い、好き嫌いなどで、なかなか共有が難しい部分もあったかもしれませんが、私はそういった垣根をできるだけなくしていきたいと思っています。

患者さんや医療従事者のために、みんなで力を合わせて、互いに情報を共有し、協力し合いながら地域医療を盛り上げていきたいです。オンラインでのやり取りでももちろん良いですが、コロナも一段落したので、フェースツーフェースで直接お付き合いしながら、これからも連携を深めていければと思っています。