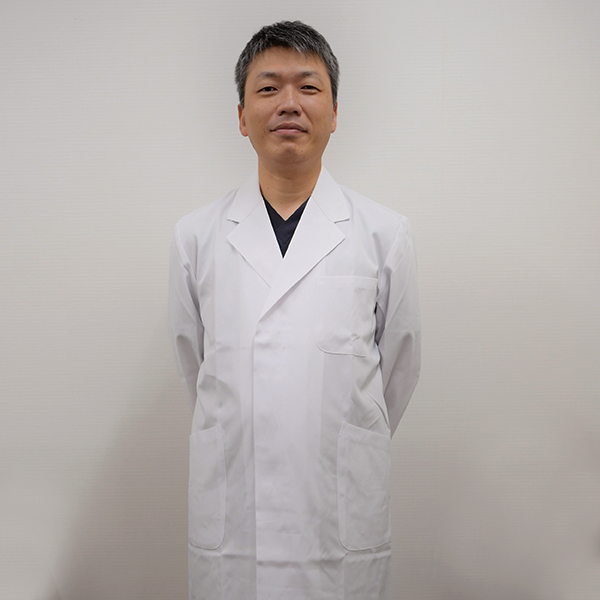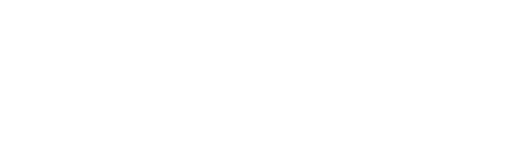リハビリテーション科 西 将則 インタビュー
日常生活を取り戻す お手伝いをするのが役目です

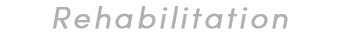
部長 兼
入退院支援センター長
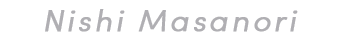
多職種のスタッフが365日、手厚くお手伝いをします
リハビリテーション科(以下、リハビリ科)に対し、一般の方はトレーニングのようなイメージをお持ちかもしれません。リハビリテーション(以下、リハビリ)は、「再び人間にふさわしい状態にしていく」というのが語源です。人としての生活をきちんと取り戻すための支援をするのがリハビリ科なので、ただ運動をやらせるというものではありません。病気やけがなどで障害を持った患者さんが自宅に帰った時、どんな生活が待っていて、どんなことに困るのか、困った時にどう対処すればいいのか、それを誰がどのようにフォローするのか、などを総合的に考えていくのがリハビリ科の医師の役目です。
障害を持った患者さんを在宅に復帰させるために、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカー、看護師、義肢装具士などいろいろな職種とコミュニケーションを取り、僕がリーダーシップを取って退院に向けた目標設定をします。当院は通常の急性期病院に比べてリハビリのスタッフ数も多いので、365日の体制も含めて手厚いリハビリを実践しています。
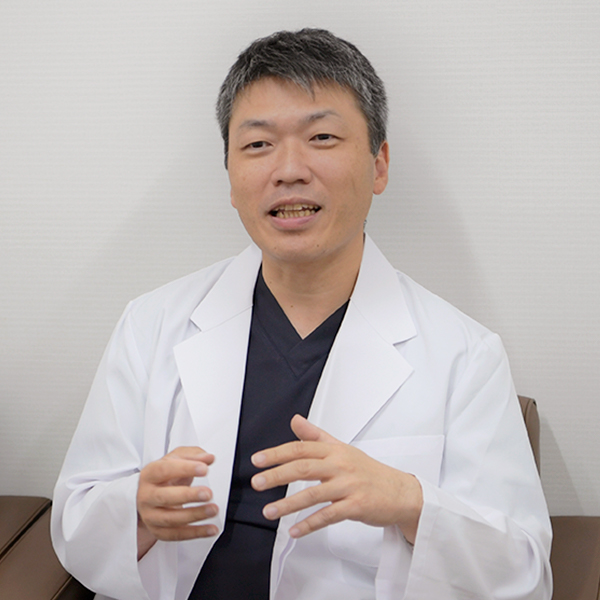
リハビリテーションの心を忘れずに患者さんに寄り添います
僕の父は歯科医で兄は集中治療医ですが、自分も医者になるとは思っていませんでした。でも、高校3年生の時に昔で言う「赤ひげ先生」のような、患者さんの心に添って働くような医師を目指したいと思い、急遽、医学部に進みました。 総合的に患者さんを診て、専門性が高い治療が必要であれば専門分野にきちんとつなげる、そういった医師でありたいと思いました。今もそうですが、リハビリ科は実はどの診療科にも関わる診療をしており、昔はリハビリ科がある病院や大学はそんなに多くありませんでした。たまたま僕がいた東京慈恵会医科大学の医局は、リハビリの分野では日本で2番目に古い歴史がありました。医局の先生は糖尿病や不整脈などの内科疾患、脳血管疾患、さらに整形疾患なども総合的に診ていたので、その姿を見て自分の思いに合う診療科はこれだと感じ、最終的にリハビリ科を選びました。
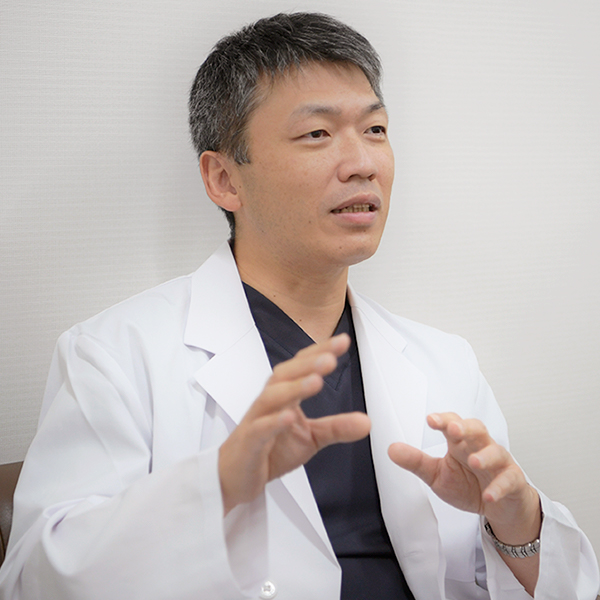
僕は「病気を診ずして病人を診よ」という言葉を大事にしています。これは母校の建学精神ですが、まさしくリハビリの心なのです。病気を治しても患者さんが寝たきりになったら話になりません。元気になって帰らないと意味がないのです。ですから、患者さんにちゃんと寄り添って、元気に帰れるような医療を提供したいと思っています。
なるべく早期に、毎日続けることが成功のカギに
大学病院やリハビリ病院での勤務や、在宅医療に携わった僕の経験上、病院で完全に寝たきりになってからリハビリをした人と、病気が発症して間もない時期からリハビリをやった人では、状態が全く違います。リハビリは最初が肝心で、そこでしくじると全てに影響することを身に染みて感じています。 土・日曜日が休みの公立病院で勤務していた時、リハビリのお蔭でせっかくできるようになっていたことが3連休明けになると、できなくなっている患者さんをよく診ていました。1日でも逃したら患者さんの回復のチャンスを失ってしまうことを実感したのです。ですから当院も365日、休みなくリハビリをすることにこだわっているのです。
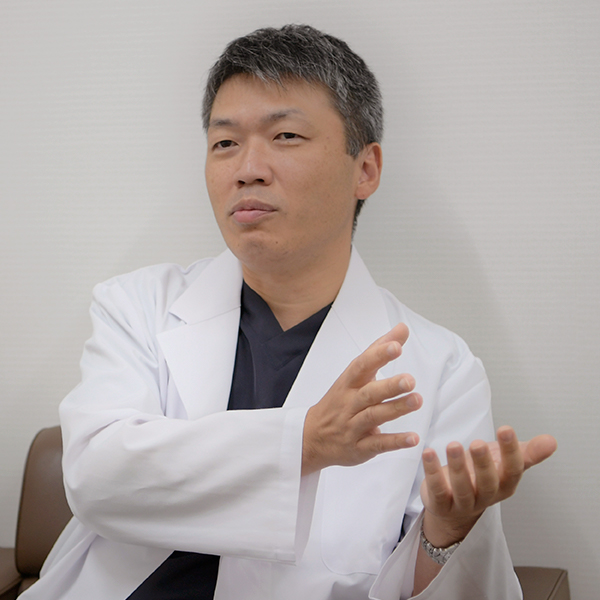
患者さんを寝かせていると筋力だけでなく、心肺機能も落ちてきて、認知症も進むことが科学的に証明されています。腹筋や背筋、お尻の筋肉などの筋肉を刺激することで分泌されるマイオカインというタンパク質は、頭はもちろん、さまざまな臓器に良い作用があることが分かっています。 手術後もなるべく早くから動くことによるメリットはたくさんあります。手術前に患者さんの体力などをしっかりチェックして、術後のリハビリの必要性をきちんと伝えることで、患者さんは手術の翌日からちゃんとリハビリができます。そこがきちんとできれば後々、リハビリもうまくいくのです。当院で最初にできることはとことんやりたいと思っています。
リハビリテーション科が一丸となってサポートします
確かに頑張ってリハビリをやっても、障害が残ることがあります。リハビリ科の医者として、どのくらい障害が残るかはある程度予測ができますので、患者さんに真実を突き付けなければならない場合もあります。しかし、やる気や希望を失わせるようなことはあってはなりません。リハビリでよくなる部分もあるのでどれぐらい良くなって、どんな生活ができるかをご説明してイメージを持っていただきながら頑張ってもらうのが、僕の重要な役割です。「ここまで頑張ったから、これだけ良くなれた」といったように患者さんに納得して帰ってほしい。ですから、どんな患者さんに対してもやり残したことが絶対にないよう、できることをやり尽くしたいと思っています。
もしもリハビリが必要になった場合、僕らが年中無休で日しっかりサポートする体制を取っていますので、ご安心ください。入院によってさまざまな不安や心配事などがあると思いますが、患者さんとお話をしながら一緒に頑張って乗り越えたいと思います。